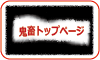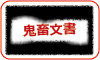鬼畜文書
村崎百郎の鬼畜流ビザール読書術
第1回課題図書:『ゴールデンボーイ』スティーヴン・キング著/新潮文庫
ナチはいいぜえ、ナチはよおおお!
(BGMは『気違いナチス』(カルカッタレコード)がおススメ)
寛大なる編集部のご好意で、醜悪な相互カマ掘り関係にある鬼畜文化とビザール文化の接点について好き放題に語れるコーナーを頂いたので、ここでは俺の大好きな精神荒廃アイテムを思いつくままランダムに紹介していこうと思う。
初回はスティーヴン・キングの中篇小説「ゴールデンボーイ」を課題図書にして、20世紀最悪といわれるナチ文化の魅力について適当なデタラメを語ってみよう。
とりあえず押さえておきたいのは「我々が日々享受する精神腐敗文化振興の最大の功労者はヒトラー総統率いるナチスドイツ第三帝国による非人道的な残虐行為の数々である」ということだ。選民意識、大量虐殺、オカルト、毒ガス、人体実験……異論はあろうがイメージとしてのナチの中には、フェチもSMも制服も変態性欲も全てが渾然一体となった強烈な磁場が形成されていて、「何にしても基本はナチだよね」という共通了解事項がビザール文化や鬼畜文化愛好家の根底にあるのは否定しようのない事実である。
良識があってなおかつ善良な尻穴の糞野郎どもが、口からアワを飛ばしてどれだけナチの非人間性や残虐性を訴えかけようとも「それにしてもナチっていいなあ!」と感動してしまう正直なビザール野郎は確実にこの世に存在する。「ゴールデンボーイ」は、そんな根性のヒネた“ナチおたく”の糞ガキが主人公だ。物語は現代アメリカを舞台に、近所に住む元ナチの捕虜収容所長の老人の正体に気づいた少年が、「よォ爺さん、黙っててやるから俺に収容所でのユダ公大量虐殺話をねんいりに聞かせろよおおおおお!」と、前代未聞のユスリをかけて、本人がもう思い出したくもない陰惨なユダヤ人捕虜大量殺戮話を毎日のように根掘り葉掘り(まるで治りかけた傷口をえぐるようにネチネチと)聞き続けるという、地獄のような設定である。明るく成績優秀な少年は、老人の語る“ぞくぞくするような”収容所の残虐非道エピソードの数々に興奮してチンポ立ちまくりで勉強も手につかなくなり成績もガタ落ちになる。老人の方も、収容所の話なんて記憶の彼方に封印していた忌わしいだけの嫌な思い出の筈なのに、少年に強要されて嫌々語っているうちに、次第にまんざらでもない気分になっている自分に気づくのだ。中でも少年が「クリスマスプレゼントだ」といって老人にナチ親衛隊の制服とブーツのレプリカを押しつけ、それを無理矢理着せて、号令をかけて部屋の中を行進させる件りのおぞましさはスティーヴン・キングの著作中でも最高峰のレベルで、俺などは何度読んでも激しい勃起が押さえられない。
少年と老人は、そうした「放課後のナチ文化強制個人授業」を通して、お互いに内に秘めた狂気と残虐性を増幅させ、夜毎悪夢にさいなまれて寝汗にまみれ、果ては浮浪者殺しにエクスタシーを感じるキチガイ鬼畜になってしまうのだ。このように「相手に寄せる信頼が全くゼロの状態で、激しく憎しみ合いながらもお互いを必要とし合う麗しい関係」などというものは、NHKの朝の連続テレビ小説を二百年間毎日観続けても絶対にお目にかかれる代物ではないので大変に貴重である。
ホラー小説に詳しい風間健二氏(4人の子持ち翻訳家/『スティーヴン・キング 恐怖の愉しみ』など著書多数)によれば、この小説は映画化も企画されていたが話があまりにリアルで陰惨なせいか、見事にお蔵入りしたとか。まあ、この内容では無理もないか……。
註:このコラム書いてから何年か経って映画『ゴールデンボーイ』は完成して公開されて観たけどなんか退屈になって途中で寝た。原作の方が妄想できるから好きかも。
第2回課題図書:『アホダラ帝国』キャシー・アッカー著/ペヨトル工房刊
それにしても昨年はずいぶんと有名人が死んだものだ。ウィリアム・S・バロウズの場合は、死んだと聞いても「歳も歳だし、あれだけさんざんヤクやってカマ掘って女房撃ち殺しても長生きできるなら人生ってイイもんだな」ぐらいの感想しか持てないが、「女バロウズ」を自称していた作家のキャシー・アッカーの訃報ともなれば「ウソだろ、まだまだ若いのに……そんなことアッカー!」と叫んだポストモダン小説愛好家は俺だけではなかったろう。末期の乳癌で死にかけているという噂は聞いていたが、何分突然のことなので、「ポール乳癌(ニューマン)!」とか「ゲイリー乳癌(ニューマン)!」などというつまらない追悼侮辱ジョークしか思いつけなかったのは、「人の不幸を己の幸福」としか感じられない鬼畜の一人として非常に残念である。このうえは、さっさと速やかに生まれ変わって、性懲りもなく愛と憎悪と暴力に満ちた強烈で凶悪な物語を生み続けて欲しいものだ。
そんなわけで、今回はパンク姐ちゃん作家のキャシー・アッカーを追悼して『アホダラ帝国』が課題図書だ。初めて読むなら性と暴力と想像力(創造力)がメインテーマのタイトル通りのフェミニズム汚穢小説『血みどろ臓物ハイスクール』(白水社刊)もいいだろうが、個人的には『アホダラ帝国』の方が馬鹿馬鹿しくて好きなのでこちらを推薦する。
簡単な略歴を記すと、アッカーは一九四八年四月十八日ニューヨーク生まれ。十代の頃から詩人やアーティストやミュージシャンなというロクでもない連中に 囲まれて育ったおかげか、七二年頃からビートの詩人と関係の深いブラック・マウンテン派の詩人として創作活動を開始。ドラッグやセックスに溺れた自らの体 験を断片的なカットアップで綴った散文作品を小さな出版社からいくつか刊行したがあまり話題にはのぼらず、生活のために42番街のポルノショーに出演した りと“身体を張って”逞しく生きていたようだ。
八〇年代に入ってから、グローブプレス社から刊行された『大いなる遺産』(思潮社近刊)、『血みどろ臓物ハイスクール』、『ドンキホーテ』(白水社刊) などが批評家たちの話題を呼び、一躍「ポストモダン・パンク小説の旗手」としての地位を確立。ルックスもモロパンクで、スキンヘッドに近いプラチナ・ブロ ンドのツンツンヘア(しかも頭のテッペンだけ黒く染めたりしてる)と、ボディビルで鍛えた身体に刻まれた大きな薔薇の刺青がトレードマーク(映画『タンク ガール』の主人公のパンク姐ちゃんみたい)。彼女について的外れなヘボい批評を書くと、ハーレーに乗って家まで直接やってこられて「何だオメーは!」とね じこまれるという怖い噂まであったというから全く大したものである。
彼女の小説の特徴は過激なまでのポルノ言語と、昔の大作家たちの小説からの「剽窃」だが、初期の小説群に通底する「私は愛さていない、もっともっと愛が欲しい」という女性特有の不毛な妄執(?)も、この『アホダラ帝国』あたりから微妙に変化して、「ああもう何でもどうでもいいや、別の神話でも作るか」的な、新しい段階に進んだような印象を受けるので興味深い。本書のストーリーはあってないようなものだが、基本は近未来を舞台にサイボーグの黒人女と、海賊に憧れるポン引きをめぐる激しいパンク話の数々だ。
ラストの“自分が何が欲しいのかもまだわかんないのか、と思った。何が欲しくなくて誰が嫌いかは充分に分かってる。それだけでも大したもんだ。”って台詞が俺は好きだぜ。
註:掲載誌の大幅更新があってこの連載は2回で打ち切りだった